
2025年11月14日コラム
犬の橈尺骨骨折が治るまでの期間はどれくらい?|治療法や注意点を獣医師が解説
小型犬や子犬などで骨折が起こりやすいことをご存知でしょうか?
特に多く見られるのが、前足にある橈骨と尺骨が合わせて骨折してしまう「橈尺骨骨折」です。
「愛犬が骨折したらどれくらいで治るの?」
「しっかり歩けるようになるの?」と不安になる方も多いかと思います。
この記事では犬の橈尺骨骨折が治るまでの期間と治療法について詳しく解説いたします。
ぜひ、最後までお読みいただき橈尺骨骨折について知見を深めてください。

犬の橈尺骨が折れてしまう原因は?
橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃくこつ)は犬の前肢(前足)を構成する2本の細長い骨です。
人間でいうと前腕(肘から手首の間)にあたる部分です。
橈尺骨は体重を支えたり、ジャンプや着地の衝撃を吸収したりする重要な役割をもっています。
小型犬は骨が細いので、ちょっとした段差からの落下でも折れてしまうことがあるため注意が必要です。
橈尺骨骨折の原因
橈尺骨骨折の主な原因は以下のとおりです。
- 落下事故
- 交通事故
- 他の犬との喧嘩
- 外傷(ドアに前足を挟む、ぶつけるなど)
- 骨の脆弱化(成長期、高齢期、栄養不良など)
特に成長期(生後3ヶ月〜1歳前後)では骨折が多くみられます。
これは骨が十分に成熟していないことが原因とされています。
成長期の子犬が抱っこから落ちてしまったり、ソファから飛び降りたりなどの出来事で骨折してしまうケースが多いため注意が必要です。
橈尺骨骨折の症状
橈尺骨骨折を起こすと、次のような症状が見られます。
- 前足を地面につけない・浮かせている
- 足を動かすと強く痛がる
- 前足が腫れる・変形する
- 鳴いたり震えたり元気がなくなる
このような症状を認めた場合にはすぐに病院に相談しましょう。
橈尺骨骨折の治療
犬の橈尺骨骨折の治療法は、骨折の種類や犬の体格、年齢によって異なります。
代表的なものをそれぞれ解説します。
外科的治療(手術)
犬の橈尺骨骨折の治療としては手術が一般的です。
手術の際は折れてしまった骨を元の位置に戻し、金属プレートやピンでしっかり固定します。
手術によって骨同士をしっかり繋ぎ、安定化させることで「骨癒合」を達成することができます。
これにより骨折の早期回復が期待でき、骨の変形を防ぐことが可能です。
また手術後は骨の癒合の状態を確認し、プレートを残すこともあれば、徐々にピンやプレートを除去していく場合もあります。
保存的治療(ギブス・包帯固定)
軽度の骨折(骨のずれが少ない)の場合では、ギプスや副木(添え木)で固定して自然に骨がくっつくのを待つ場合もあります。
ただし、小型犬ではギプスだけでは安定しないことが多く、再骨折のリスクがあります。
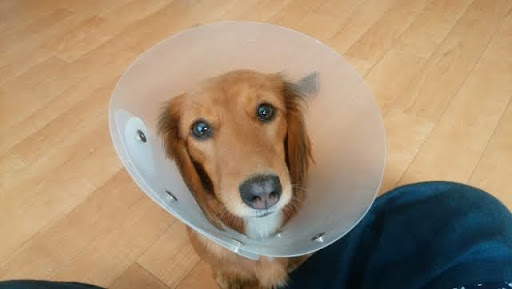
橈尺骨骨折が治るまでの期間
橈尺骨骨折が治るまでの期間は、骨折のタイプや治療法によって異なります。
治るまでのおおよその期間を治療別に解説いたします。
外科手術(プレート固定)
プレートの固定期間(骨癒合まで)は犬のサイズ別に以下の期間が目安となっています。
- 小型犬:約6〜8週間
- 中型犬:約8〜10週間
- 大型犬 :約10〜12週間
骨癒合が完了する時期は若齢の犬や小型犬が比較的早く、高齢犬や大型犬になると長い期間を要する場合があります。
橈尺骨骨折の手術後は約2週間は完全に安静な状態を保ち、術後2〜3週間から軽い歩行など少しずつリハビリを始めていきましょう。
橈尺骨骨折の手術後は、通院しながら骨折の治り具合を確認し、約2ヶ月ほどで通常の生活に戻れることが多いです。
保存療法(ギプス固定)
ギプス固定による保存療法は骨の癒合までに8〜12週間、完全に歩行ができるようになるまで約3〜4か月(またはそれ以上)ほどかかります。
外科手術を行った場合より、治療期間は長くなることが多いです。
治療中に気をつけたいこと
犬の骨折を早期に治すにはさまざまなことに気をつける必要があります。
安静にする
治療を受けたあとには、安静にすることが重要です。
ソファ・ベッドなどからの飛び降りは再骨折の危険があるため注意が必要です。
どの程度の運動が可能かは治療の進み具合によって異なるので、担当の獣医師に確認しましょう。
患部を清潔に保つ
患部が不衛生な状態になると、そこから感染が起きて皮膚の状態が悪化することがあります。
包帯やギプスが濡れたりしないよう清潔に保っていきましょう。
体重管理をする
体重が増加してしまうと骨への負担が増えます。
治療中も治療後も適正な体重を保つように心がけましょう。
定期的に通院をする
骨折の治療を受けたあとは必ず定期的に病院に通い、レントゲンなどで骨の癒合の確認を行います。
小型犬は治療後の再骨折も多いため、早めに異変に気がつけるようにすることも重要です。
栄養管理
骨折の治癒には適切な栄養をとることも重要です。
バランスのとれた食事を心がけましょう。
骨折の治りが遅くなってしまうケース
以下のような場合は橈尺骨骨折の回復が遅れることがあります。
- 安静にできなった
- 感染症(骨髄炎)が起きた
- 固定が不十分だった
- 栄養不良が起きた
- 高齢・持病(糖尿病、ホルモン疾患など)などの影響がでた
骨折の治療を問題なく進めるには、ご自宅での適正な管理と定期的な通院が重要となります。

まとめ
犬の橈尺骨骨折は治るまでに長い期間を要します。
しかし早めに発見し適切な治療を行えば、治るまでの時間を短くしてあげることが出来ます。
また小型犬では特に、治療後も再骨折しやすいのでしっかり安静を保ちこまめに通院をすることも重要です。
当院は整形外科を強みにしています。
犬の前足が折れたかも、と気がついたらすぐに当院にご来院ください。
神奈川県藤沢市の動物病院
辻堂犬猫病院